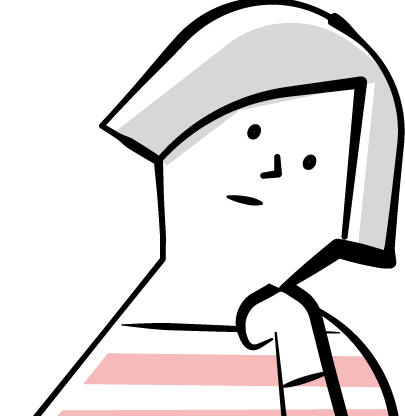
モンテッソーリ教育って聞いたことあるけど、そもそもどんな教育のこと?
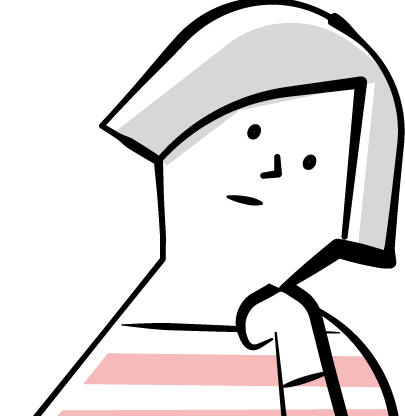
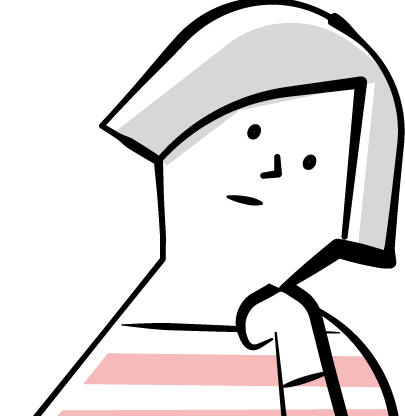
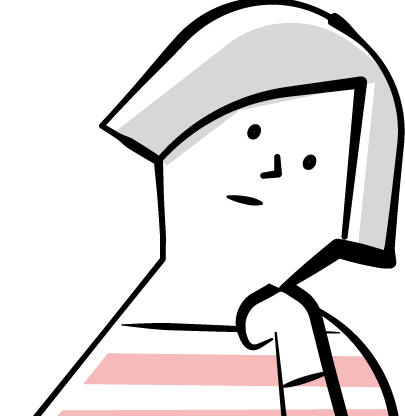
モンテッソーリ教育を受けることでどんな子に育つの?
こんにちは!
マムミーライフのユウです。
2歳差の姉妹ママです。
今回は『モンテッソーリ教育とは?』について、はじめて「モンテッソーリ教育」という言葉を聞いたという方向けに、できるだけ簡単に、誕生の背景や欠かせないキーワードなどを分かりやすくご紹介していきたいと思います。
我が家の2人の娘たちは、現在モンテッソーリ教育を長年取り入れている保育園に通っています。
通い始めて約1年ですが、成長ぶりには驚くことばかりです。



私自身モンテッソーリ教育の考え方を知り、今までとは違った目線で子どもを見ることができ、子育てがラクに、楽しく感じるようになりました。
モンテッソーリ教育は「オルタナティブ教育」の一つで、『子どもの自主性を尊重する』教育法です。
オルタナティブ教育とは?
「オルタナティブ=もう一つの」という意味で、国が定めた学校教育法に替わる、従来の義務教育とは違う第三の新しい教育法のことをいいます。



その中でも日本でよく聞くのは「モンテッソーリ教育」と「シュタイナー教育」かな~



そうそう!
私も長女の保育園を探し始めた時に、ちょうどいろんな教育法を知って実際に見学に行ってみました!
日本国内では幼児教育として注目を集めていて、モンテッソーリ教育を取り入れている幼稚園や保育園は多数あります。
本来のモンテッソーリ教育の考え方では、人間として完成するのは24歳頃までと考えられていて、発達を4段階に分けています。
| 第一段階☆ | 乳幼児期 | 0~6歳 |
| 第二段階 | 児童期 | 6~12歳 |
| 第三段階 | 思春期 | 12~18歳 |
| 第四段階 | 青年期 | 18~24歳 |
この中でもマリア・モンテッソーリは、0~6歳までの乳幼児期を「その後の長い人生に必要な80%の能力を身につける最も重要な時期」としています。
6年間を前期(0~3歳)、後期(3歳~6歳)に分け、それぞれ前期には7つ、後期には5つの教育環境(分野)が準備されています。
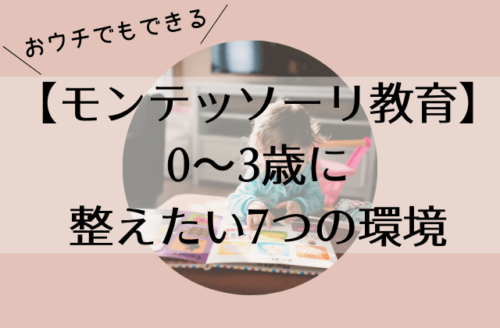
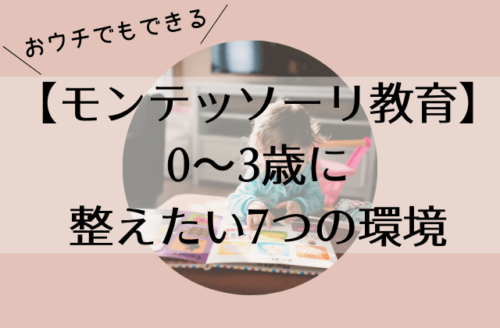
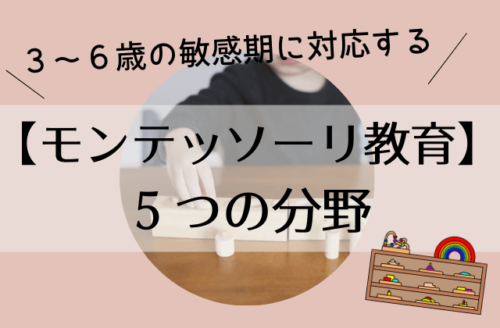
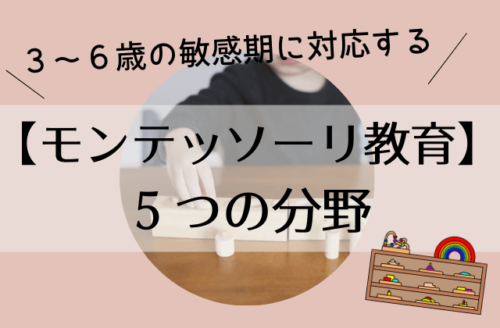
環境を整え適切にサポートしてあげることで、子どもが本来持っている「自己教育力」を身に付けることができると考えられています。
さっそく「モンテッソーリ教育とは?」について基本的なことから紹介していきます。
そもそもモンテッソーリ教育とは?


モンテッソーリ教育とは、イタリアのローマ大学で女性で初めて医学博士となった『マリア・モンテッソーリ』が提唱した教育法のことをいいます。
誕生の背景
マリア・モンテッソーリは、精神病院で知的障がい児の教育を担当し、子どもの知能を向上させることに成功しました。
1907年に設立された貧困層の家庭の子ども達を対象とした保育施設「子どもの家」においても、子どもが本来持つ能力を適切なサポートで引き出すことに成功し、その教育法を確立させていきました。
その後、欧米を中心に世界中に広がっていき、アメリカではモンテッソーリブームが2度にわたっておこり、今ではモンテッソーリ教育を行う学校や「子どもの家」が3000ヵ所以上あるといわれています。



誕生から100年以上たった現代でも多くの人たちに支持されているんだね。
モンテッソーリ教育を受けた有名人
モンテッソーリ教育を受けた有名人として、Amazonの創始者・ジェフベゾス、Googleの共同創設者・セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジーなどが有名です。



世界中の人が知っているサービスを創り出した人たちだね。
他にもたくさんの著名人の名が挙がっており、モンテッソーリ教育は100年以上経った今でも、たくさんの支持をうけています。



イギリス王室のウィリアム王子やその息子のジョージ王子もだってね!



日本ではプロ棋士の藤井聡太さんが受けていたことでモンテッソーリがひときわ注目を集めたよね!
モンテッソーリ教育の特徴
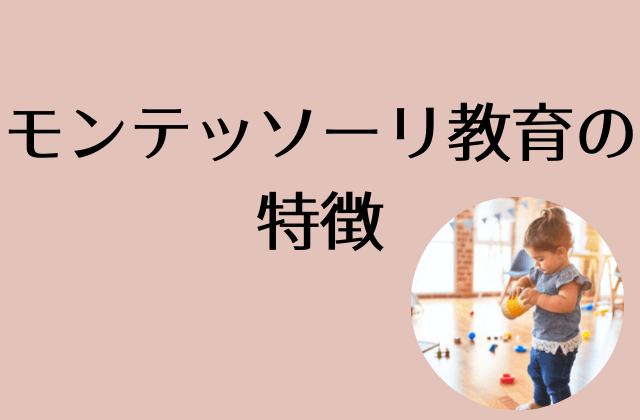
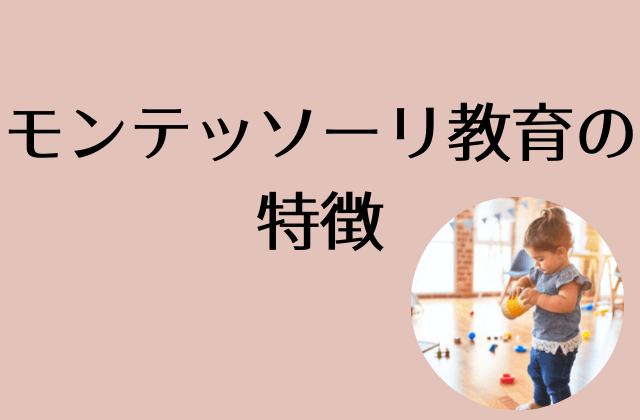
目的
モンテッソーリ教育の目的は、「子どもには自分で自分を教育する、育てる力がある」という『自己教育力』を身に付けることです。
子どもたちが自発的に行動し、活動に取り組むことが尊重されています。
モンテッソーリを取り入れている園の特長として、「おしごと」といわれる活動の時間があり、大人が考えた順番やカリキュラムを“みんなで一緒に”進めるのではなく、自分の興味のあることに自由に取り組むことができます。
欠かせない3つのキーワード
モンテッソーリ教育とはなにか?を理解する上で、欠かせない3つのキーワードについて解説します。
- 自主性
- 整えられた環境
- 敏感期
1.自主性
モンテッソーリ教育の中でも一番よく聞くのがこの『自主性』という言葉。
大人が主体ではなく、子どもが自分でできるように見守る。
自主性を育てるのがモンテッソーリ教育の大きな目的です。
2.整えられた環境
子どもが“ひとりでできるようになる”ために「こどもの自主性を発揮できる環境を整えること」。
それが大人(教師)の役割だとマリア・モンテッソーリは言っています。
大人は子どもの「自分でやりたい」を邪魔せずに、見守ることが大切と考えられています。
これはなんでも自由にさせ放っておくのではなく、子どもの『敏感期』を逃さないよう適切にサポートしながら見守ることが重要で、大人(親や教師)も人的環境という「整えられた環境の一つ」という位置づけです。
3.敏感期
子どもには、“何かに強く興味をもち、同じことをくり返す時期”があります。
それをモンテッソーリ教育では『敏感期』とよんでいます。
0~6歳のさまざまな敏感期
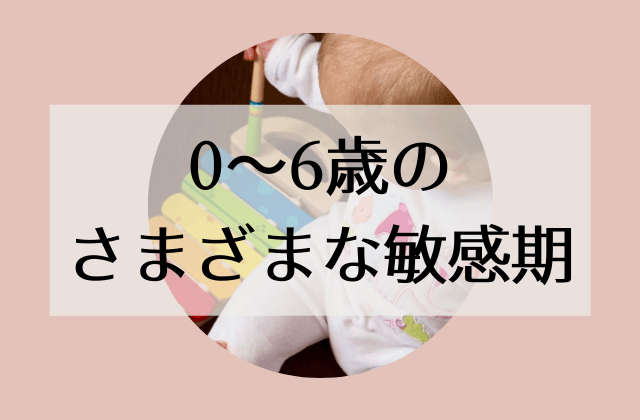
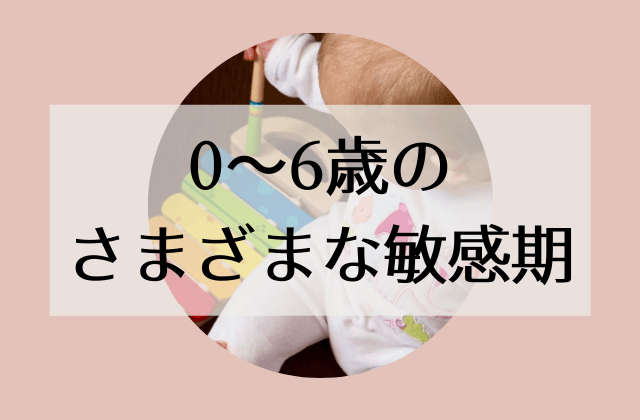
子どもが成長する過程で、ある一定の期間何かに興味をもち、熱心に取り組む時期。
これが【敏感期】です。
モンテッソーリは、小さな赤ちゃんが人間として大きく成長していく0~6歳の時期にさまざまな能力が顕著に現れることを知っていたので、この『敏感期』が人間にも当てはまるのではないかと考えました。
0~6歳の間にみられる敏感期にはさまざまなものがありますが、一例をご紹介します。
(目安:生後6か月~3歳前後)
ピークは2歳半~4歳くらいともいわれています。
この時期はこだわりが強く、順番や場所・やり方・位置などにとてもこだわります。
いつもと違う道を通ることが許せなかったり、特定の場所にこだわり譲らないなど、大人からすると一見ワガママに思えることですが、これは「秩序の敏感期」のあらわれです。



2歳の次女はまさしく、今「秩序の敏感期」のピーク!
これを意識するようになって、私もラクになったし次女のぐずりが減りました!
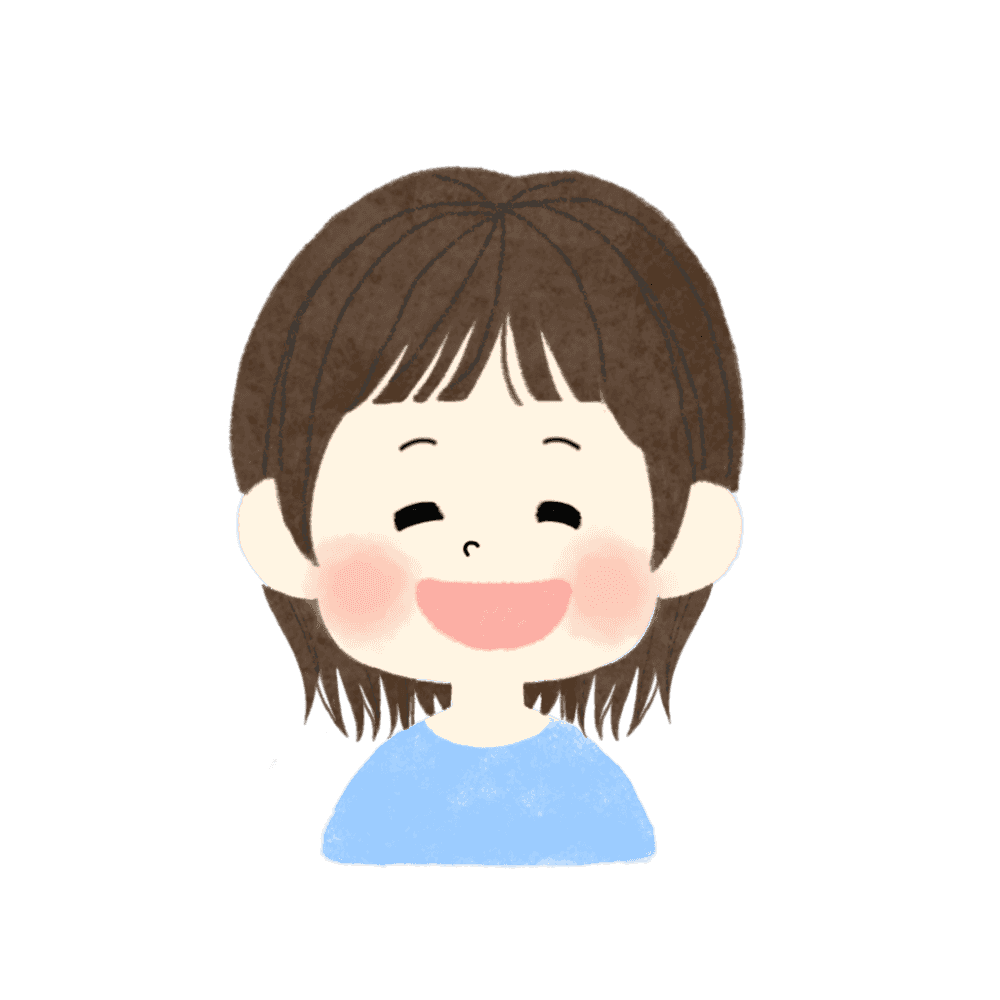
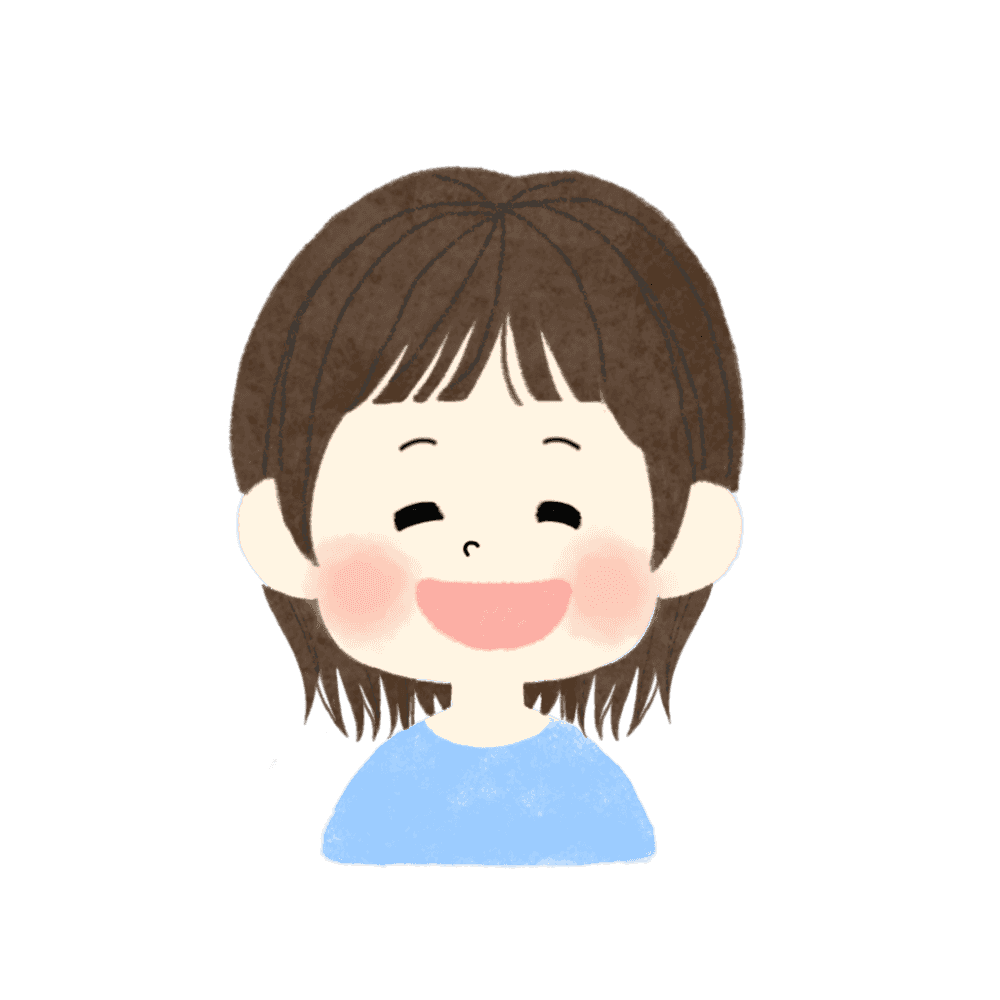
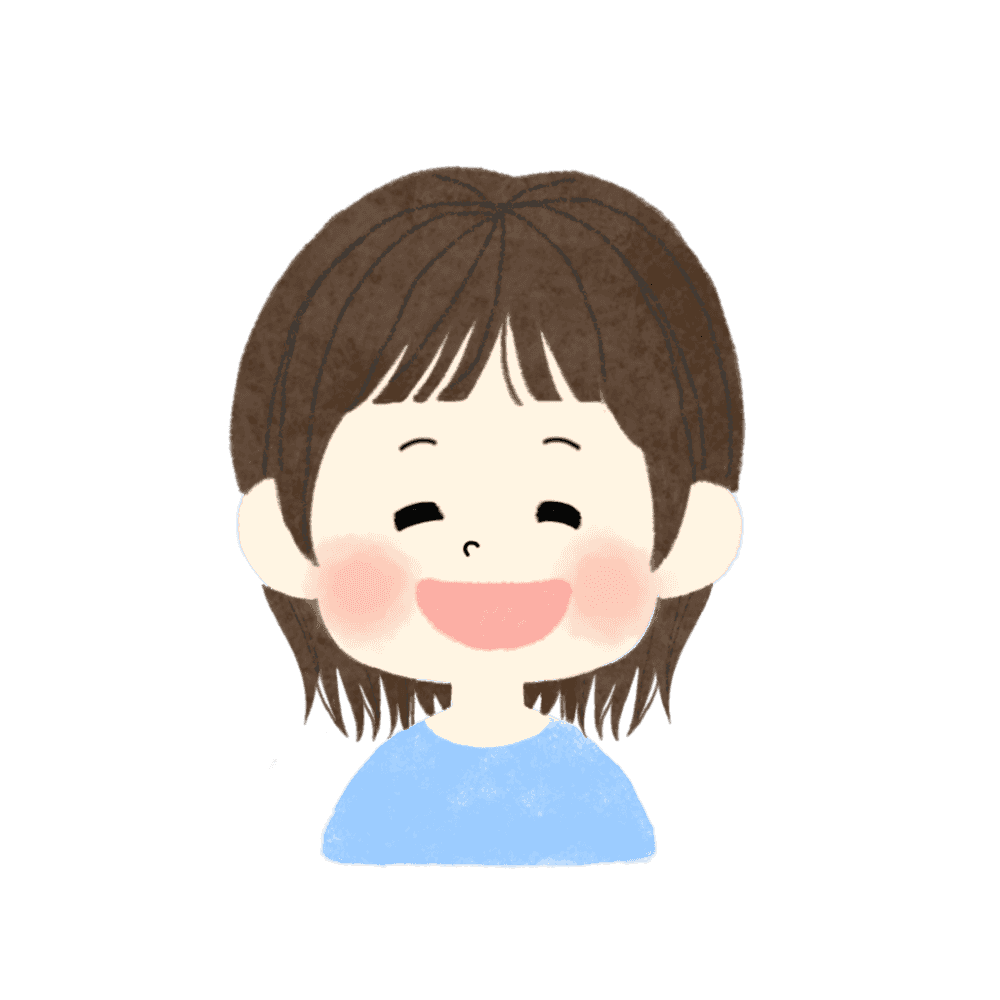
ママに分かってもらえると嬉しい
(目安:胎生7か月~5歳半くらい)
どんなことばも習得できる時期。
3歳前後までの「はなし言葉」と、3歳半~5歳半頃までの「文字ことば(書き言葉)」の2つがあります。



お腹の中にいるときからなの!?



胎生7か月頃になるとすでに聴覚は完成していて、 どんどん言葉を吸収する時期が始まっているんだよね。
お腹の中にいた頃も呼びかけるとポコッて反応してくれたりしたな~
(目安:3歳半~4歳半)
書くことに夢中になる時期。
大人が書いているのを見て覚えていくので、書く姿を見せてあげることも大事です。



長女もひらがなや数字が読む→書けるようになって、お手紙をよく書いているな~



“まま だいすき”って一生懸命書いてくれたお手紙は嬉しいよね
(目安:4歳~6歳)
多い・少ない、順番など日常生活の数的な要素に敏感になる時期。
車に乗っているときに、通りすぎる車のナンバープレートに興味をもったり、おやつの数を数えたりしているときは『数の敏感期』です。



長女が今ちょうど「書くこと」や「数」の敏感期かな~



いつもお手紙や数字を夢中になって紙に書いてるよね!
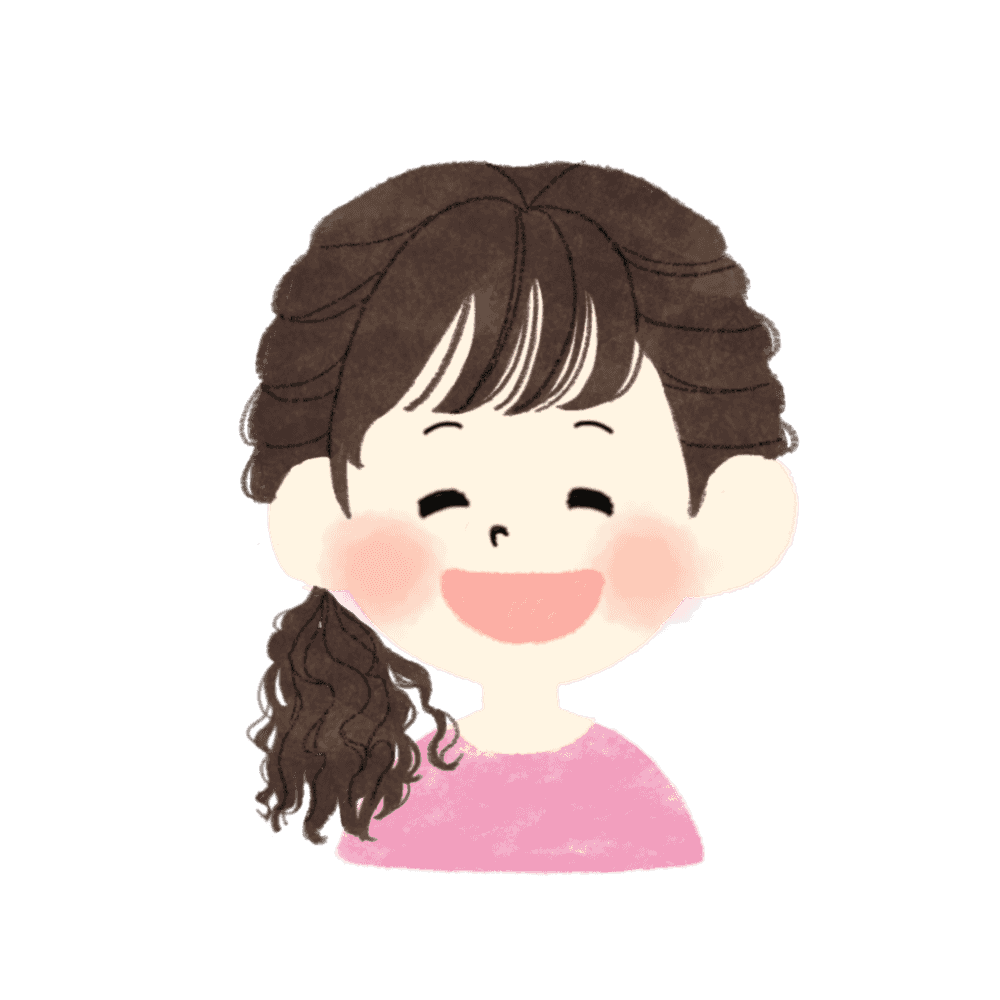
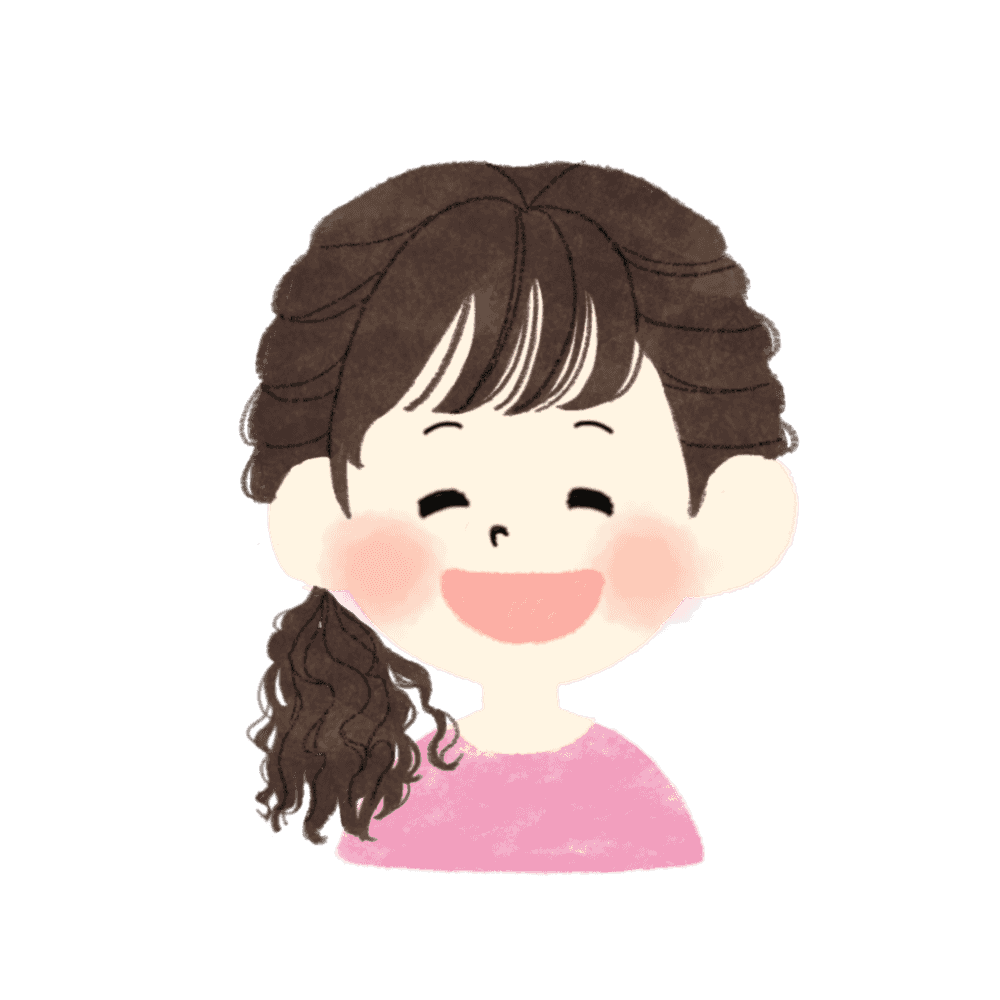
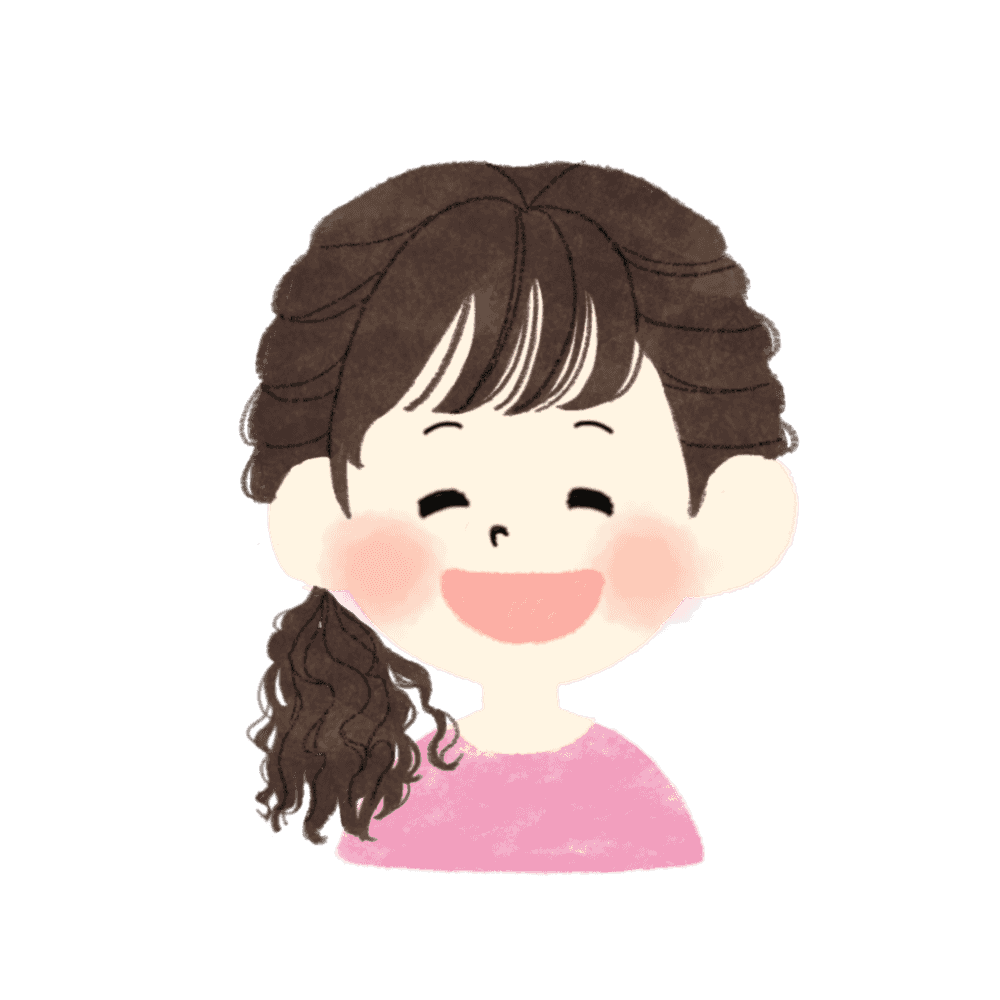
ママー!お手紙どーぞ!
『敏感期に気づいてあげる』
他にもさまざまな敏感期がありますが、おとなは勝手に「イヤイヤ期だ」と片付けてしまったり、おとなの都合に合わせようとしてしまいますよね。
・子どものその時しかない貴重な敏感期に気づいてあげること。
・子どもをよく観察し、やりたいことを理解してあげる、満足のいくまでやらせてあげること。
日々の忙しい生活で、100%子どものペースに合わせることは難しいかもしれませんが、今しかない『敏感期』を可能な限り伸ばし、サポートしてあげたいですよね^^
私は『敏感期』という子どもの発達の一つを知ることができて、子どもの様子を今までと違った目線で見れるようになりました。
慌ただしく大変な育児の中で、子どもの成長を感じ取れる楽しさを見つけることができたんです。
同時に、子どもの新しい表情とも出合えました。
ちょうど乳幼児期のお子さんのいるママ・パパには『敏感期』について、時期を逃す前にぜひ知っておいてほしいなぁと思い別の記事でもう少し詳しくまとめてみました。
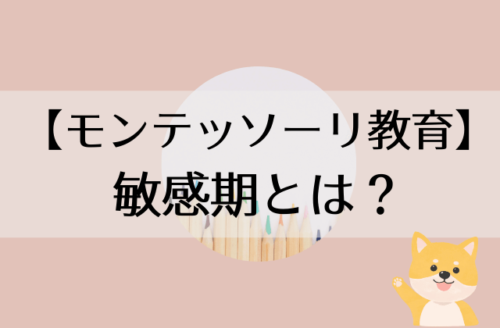
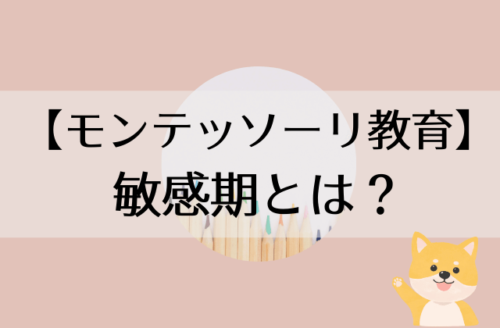
モンテッソーリ教育の教育環境(分野)【前期と後期】
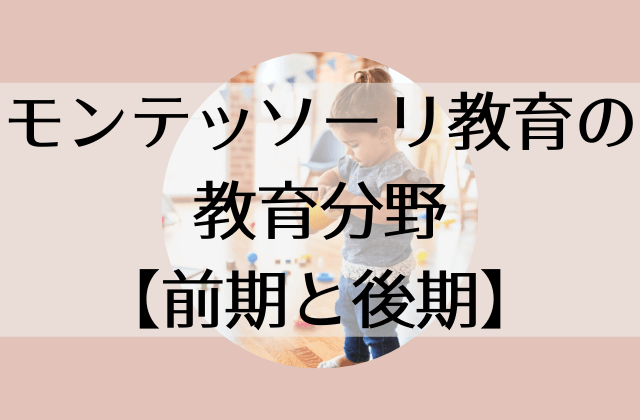
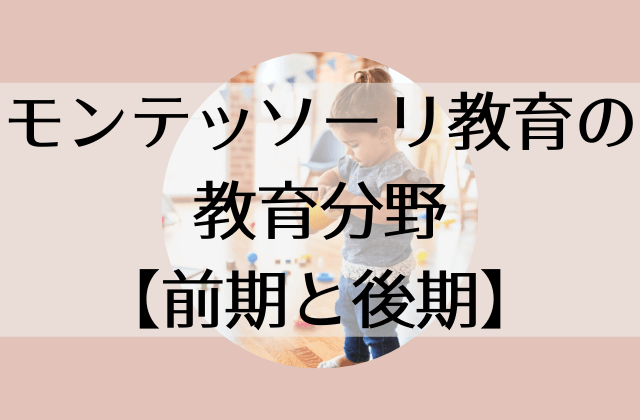
モンテッソーリ教育では、乳幼児期の発達段階に合わせ、いくつかの教育分野に沿った環境が準備されています。
それぞれの教育環境に適した「モンテッソーリ教具」があり、それらを活用しながら能力を伸ばしていきます。
『おしごと』とよばれる活動の時間に、それぞれの敏感期に合わせて、興味のある活動を自分で選び、活動し、自己教育力を高めていきます。
①粗大運動の活動
②微細運動
③日常生活の練習
④言語教育
⑤感覚教育
⑥音楽
⑦美術
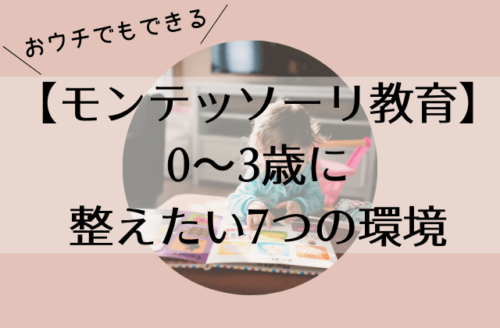
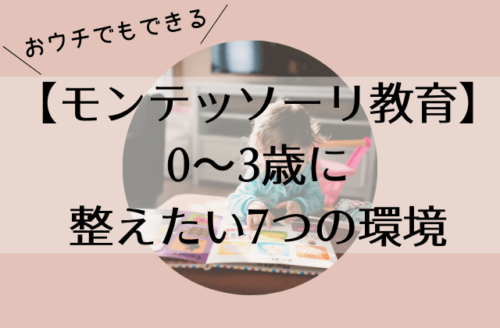
①運動(日常生活の練習)
②感覚
③言語
④算数
⑤文化
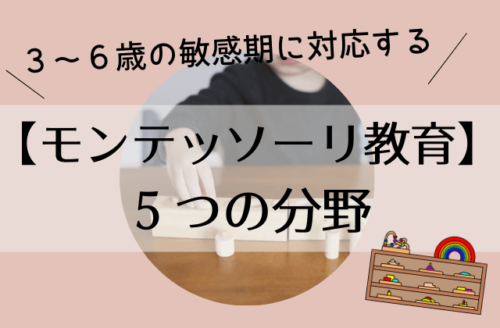
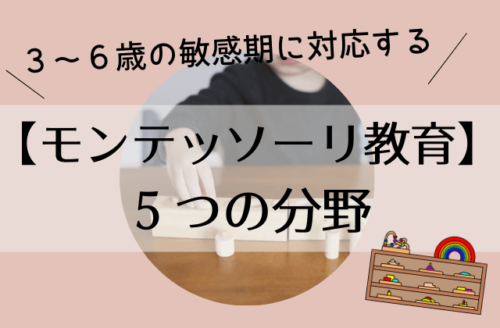
我が家は、長女が3歳半、次女が1歳半の時に入園したので、【前期と後期】の両方の環境での成果を子どもの成長を通じて感じています。
モンテッソーリ教育のメリット・デメリット
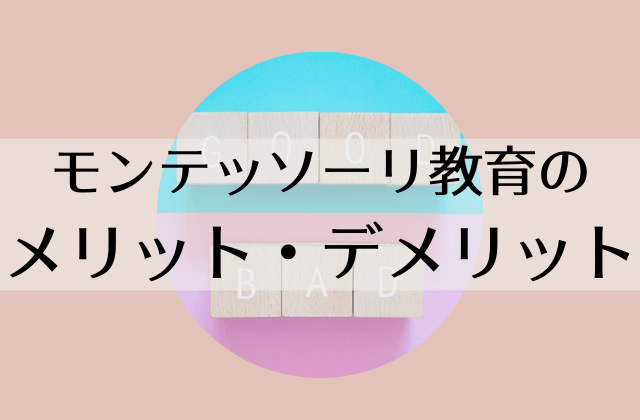
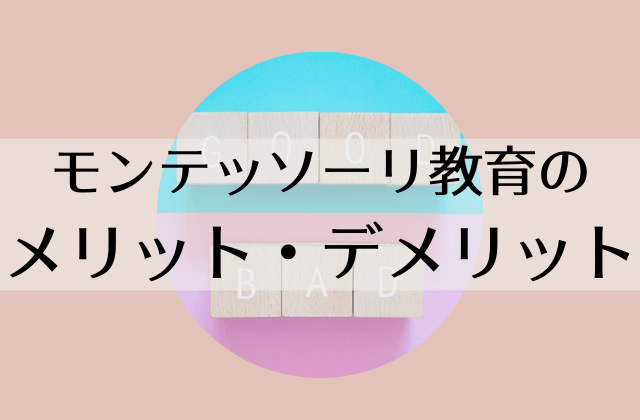
よく挙げられるモンテッソーリ教育のメリット・デメリットについてご紹介します。
○自立できる
モンテッソーリ教育では、年齢の違う子ども達が一緒のクラスで活動する「縦割りクラス」が特長です。
年少さんは年長さんの姿をみて成長しますし、年長さんは年少さんのお手本になることでさらに成長します。
○積極性が身につく
“おしごと”と呼ばれる活動の時間は、自分のやりたいことを自分で選択します。
そうすることによって、積極性が身についていきます。
○集中力が養われる
おしごとの時間内は、大人が途中で手出し・口出しはしません。
(見本をみせるなどの適切なサポートは必要に応じてしています)
おとなに邪魔されることなく、自分の好きなことに夢中で取り組むことで集中力が養われていきます。
○情緒が安定する
大人の手を借りることなく、「自分でできた!」をくり返すことで達成感を感じ、自信にもつながります。
その成功体験を積み重ねていくことで心が落ち着き、情緒が安定していきます。
○協調性がない、集団行動が苦手
こどものそれぞれの興味に合わせて、自由に活動に取り組む環境が当たり前のモンテッソーリ教育は、まわりと協調して動くことが苦手になるのではという声があります。
ですが、実際にモンテッソーリ教育の園に通わせている親としては、決められた時間内に自由に活動できるおしごとの時間以外はご飯、おひるね、遊ぶ時間など、自由の中にも規律もあり、しっかりと周りと同じように行動する時はする、というメリハリはできているようなので、私自身はとくにデメリットに感じたことはありません。
○動くことが大好きな子には向かない
教具を使った屋内での作業が中心なので、体を思いっきり動かすことが大好きな子には向かない、というようによく言われています。
モンテッソーリ教育の提唱している教育環境の中に「粗大運動の活動」というものもあります。
これは体の大きな動きを発達させるように促す活動です。
この活動をしっかりと体験させるからこそ次の「微細運動の活動」という手先や指先を使った活動もスムーズに進めるようになります。
娘たちが通っている園でも、朝と昼食後、帰りのお迎えの時間など、たっぷりと園庭で遊ぶ時間があります。
食が細かった長女も、屋内の活動で手先や頭を使い、外でもしっかり遊ぶためよく食べるようになりました。
モンテッソーリ教育は屋内での作業中心というわけでは決してありませんが、スクールや園によっては、園庭がなかったり狭かったりと環境が違うと思いますので、園選びの際はしっかり確認することも必要かもしれません。
そして子どもの様子をみて物足りないようなら、休日は公園などで思いっきり遊ばせたり、スポーツ教室などでからだを動かす機会を設けることを考えてもいいのかもしれません。
家庭でできるモンテッソーリ
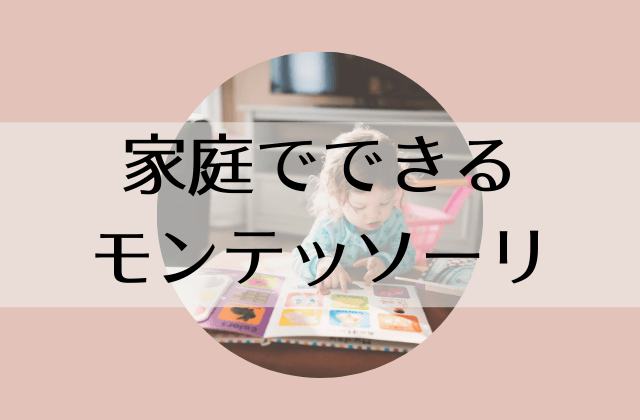
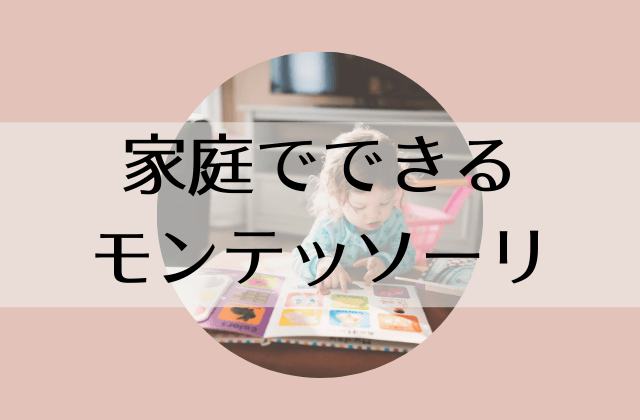
モンテッソーリには『教具』と呼ばれる、子どもの発達に役立つ道具がたくさんあります。
しかしマリア・モンテッソーリは教具について「モンテッソーリ教育における最も重要な要素では絶対にない」と述べています。
モンテッソーリ教育での基本的な考え方は、『子どもは生まれつきだれでも、自分の力で成長しようとする能力を持っている』ということ。
・子どもが能力を発揮するのを邪魔しない。
・自発性を尊重し、子どもが自分の意思で自由にできるようにサポートしてあげる。
・子どもの敏感期を満足させるような環境を整えてあげ、大人はそれに気づいてサポートする、見守る、口を出しすぎない
このポイントを頭にいれておくだけでも、教具がなくても、園に通えなくても、家庭でモンテッソーリ流の子育てができ、子どもが本来持っている「自己教育力」を伸ばすことができるのではと思います。
モンテッソーリ教育に関する本
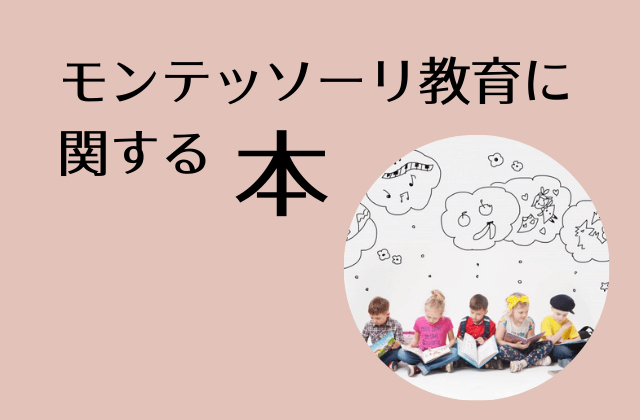
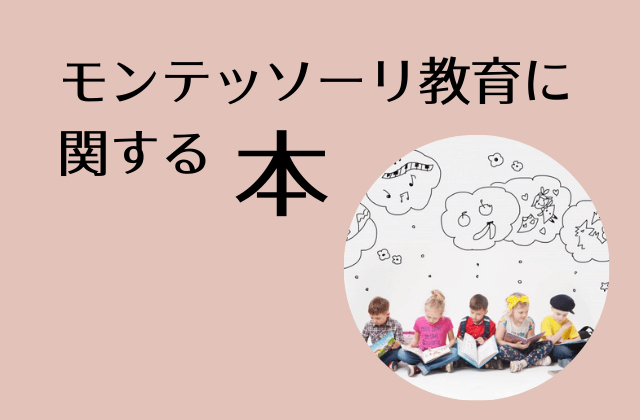
モンテッソーリ教育に関しては、本もたくさん出版されています。
基本情報や実際のエピソード、分かりやすいイラスト付きで簡単に家庭で取り入れられる方法だったりさまざまです。
・モンテッソーリ教育を受けられるスクールや園を探している。
選ぶ基準にするためにも詳しく理解したい。
・子どもの自主性や個性を伸ばすために、家庭で取り入れてみたい。
などなど、自分の知りたい事や好みに合わせてぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
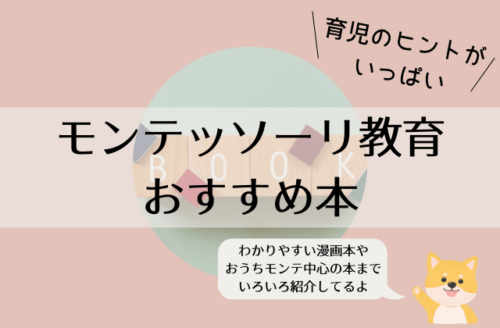
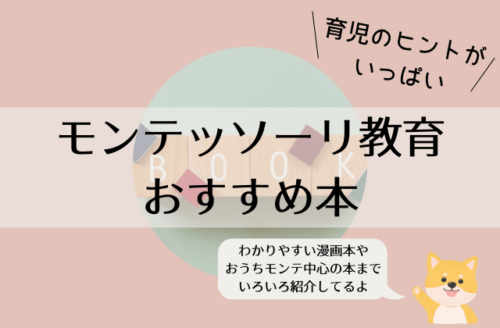
まとめ
今回は、モンテッソーリ教育とは?について基本的なこと、モンテッソーリ教育を語るうえで欠かせないキーワードや特徴についてご紹介しました。
実際に子供たちがモンテッソーリ教育の園に通いはじめて1年。
しっかりと研修を受け、子どもの発達についても理解してくださっている先生方に見守られながら過ごしているので、子ども達はのびのびと楽しんで過ごし、日々成長しています。
2歳半の次女は、長女が2歳半の時には出来なかったこともいつの間にか当たり前のようにできるようになっています。
それは長女が出来なかったのではなく、親である私自身が“まだ小さいから…”となんでもやってあげたり先回りしてしまい、『できる環境を整えてあげられてなかっただけ』だと痛感することも多いです。
「子どもは、自分の力で成長しようとする力をもっている」ということを、整えられた環境と先生方の適切なサポートの中で日に日に成長していく娘たちをみて実感しています。


一番大切なのは、方法や手法にこだわるのではなく、目の前の子どもたち自身が自分でできる能力を邪魔せず、いいところを伸ばせるよう適切にサポートする、優しく見守るということだと思います。
我が家は近くにとても良いモンテッソーリ教育の園があったので通わせることができていますが、近くに良い園がない、見つからない、という場合もあると思います。
ですが、モンテッソーリ教育の一番の目的は、『子どもの自主性を育むこと』です。
・自分の子どもに合いそうな部分を家庭で取り入れてみる。
・子どもを理解するために、モンテッソーリ教育の考え方を参考にしてみる。
そんな活用の仕方でもいいのではないかなぁと思います。
一番は、方法や手段にこだわるのではなく、『ママも子どもも笑顔で過ごせること』。
これに尽きると思います^^
―モンテッソーリメモ―
・環境を整えること
・子どもを一人の人間として尊重する
・大人の役割を理解する
・敏感期を逃さず見守り、サポートする。



さぁ今日も『秩序の敏感期』真っ只中の次女の笑顔を守るために、がんばるぞー!笑



ママファイトー!
お問い合わせ
マムミーライフのページにご訪問いただきありがとうございます。
・ママとして子どものことを考える時間
・一人の人として”どんなわたしでいたいか”を考える時間
【Mom(マム)+Me(ミー) Life】は、そのどちらも楽しめるように。
・わたし自身が詳しく知りたかった情報
・小さなお子さんのいるママに役立つ知識や情報
心がちょこっと軽くなって笑顔になれるようなテーマを中心に書いています。
記事の感想や子育ての悩みなど、なんでも気軽にお寄せいただけると嬉しいです^^
また、内容に関しては正確な情報をしっかりお伝えできるよう十二分に配慮していますが、古い情報、間違った情報などありましたらお問い合わせフォームからご意見をお寄せください。
お問い合わせはこちらから
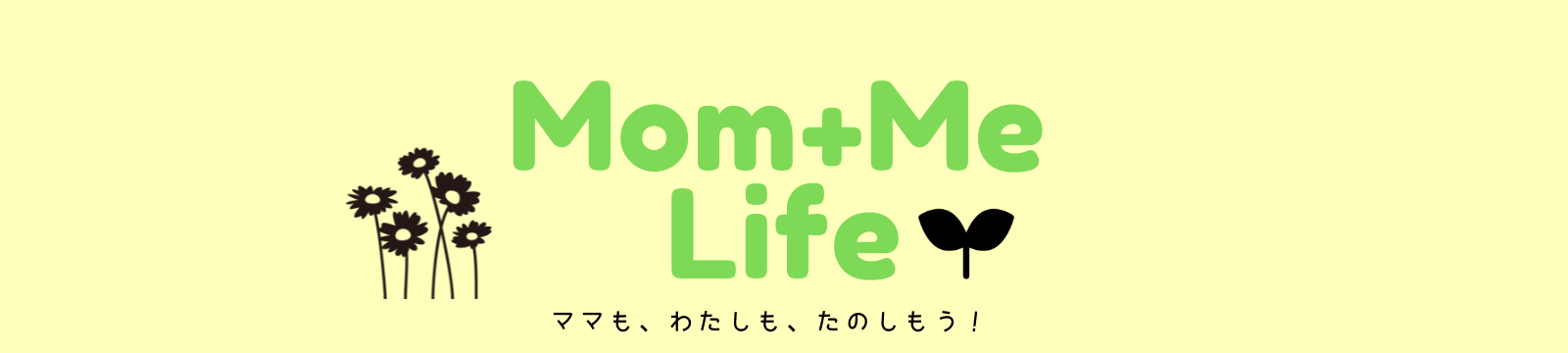

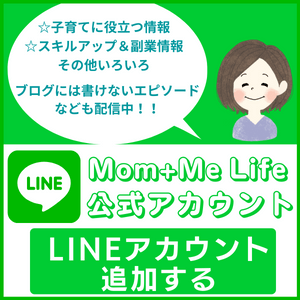
コメント